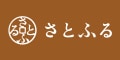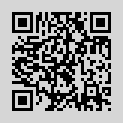原産地呼称の考え方 ①
今日から、訳ありで少しだけ、ワインに関することをお話させていただくつもりです。テキストが多くなるかもしれませんが、少しの間おつきあいください。
ワインに関しましては、素人の半可な部分もあるかもしれませんので、間違いなどありましたら遠慮なしにご指摘いただければ幸いです。
ワインの場合は、原産地に関する思いといいますか、文化、風俗に対する敬意からか、それは厳格に国の法律によって定められていることがあります。
例えば、フランスのAOC やイタリアのDOC,DOCG,IGT,Vdtなどですね。
オーストラリアのタスマニアなども厳しいワイン法があると聞いたことがあります。
このあたりはウィキペディアにもかなり詳細に掲載されておりますので、そちらを読んでいただくといたしまして、なぜワイン(あるいはチーズ、バターなど)はここまで厳格に原産地、あるいはそれに伴う製法、品種などに決まりがあるのかということです。
コーヒーにも生産国ごとに、おもに外観上のスペックで等級を分けたりする制度を持っていたりするのですが、原産地統制というコンセプトではないようです。
出自にこだわるヨーロッパ民族独特の考え方と言ってしまえばそれまでですが、それだけではないようです。
そういば、長野県(ワイン、米、焼酎など)なども田中元知事などが中心に原産地呼称制度を導入しておりますね。
よく例として出させていただくシャンパーニュ。
日本では、泡の出るワインはみんなシャンパンと言われている感もありますが、正式には「フランス シャンパーニュ地区で作られたぶどうで(品種も定められている)、法律で定められたシャンパーニュ方式で作られた発泡性のワイン」ということになるでしょうか。
AOCには勿論官能評価もありますが、ここを破ってしまいますと官能評価までいきません。(ワインの場合、これらの法律による格付け=味の格付けとは限りません。実際にには2級を越える4級ですとか、DOCGを越える評価のVdtというのは多くあります。)
また、シャンパーニュ地区産であっても、法律から外れた方式、使用品種などを採用すればその時点でシャンパンは名乗れないですし、逆に、たとえフランス産で、シャンパーニュ方式に則って作られた発泡性ワインであったとしてもシャンパーニュ地区を一歩出て作られたものだとシャンパンは名乗れないのです。
上述させていただきましたシャンパン以外の発泡性のワインはシャンパンは名乗れず、発泡性ワインの一般呼称であるスパークリングワインとして販売されます。
(勿論、シャンパンを呼称できない味の優れたスパークリングワインは世界中にたくさんあります。)
自由な国?日本からいたしますと、何でそんなに厳しく、細かくしなければならないんだとなるかもしれませんが、ここをきちんとしておきませんと、文化を守るということもあるでしょうけれども、原産地固有の価値を守ったり、高めていくことが難しくなるということだと思うんです。
彼らは、長い歴史の中でそれを学び、自ら生きていくために制度、法律に置き換えてきたといえるのではないでしょうか。
「何でもアリ」、という風にしてしまっていたら、シャンパンという呼称そのものがなかったかもしれませんし(呼称する意味がない)、シャンパンに限らずスティルワインでも同じ村、地区だけではなく、北部南部のブレンド、あるいは国をまたいでのブレンドなどもワインで主流になっていたかもしれません。(実際には主流ではありませんが、ありますね)
勿論呼称だけではなく、原産地ならではの味の個性を守るということも重要なことですね。
色々な要素(例えば、味や価格)が良くも悪くも、ならされて、今よりもずっと平均化していたと思われます。
もっと言いますと、ワインというものがこれほど嗜好性が高く、多くの人が楽しめる飲み物になっていなかった可能性もあります。
今日のブログのお話を要約いたしますと、以下のようになるでしょうか。
①ワインに関する法律は何故出来たのか
②原産地の価値、テロワールの違いによる個性を守る
③嗜好性の高い飲み物をつくること